
個人事業主の会計方式は、税込が基本です。
個人事業主の消費税、会計処理はどうする?

帳簿を作る上で、面倒な会計処理が消費税の計算です。
個人事業主は、消費税を、税込経理方式と税抜経理方式のどちらで会計処理すればいいのでしょうか?
消費税の免税事業者は必ず税込経理方式。

小規模な免税事業者の個人事業主は「必ず税込」です。
年間の売上が1000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、必ず税込経理方式で会計処理します。
消費税を税別で処理する、税抜経理方式を採用することはできません。
税込経理方式では、支払った消費税は全て総額で経費として会計処理して、受け取った消費税は全て総額で売上として会計処理します。
帳簿は、消費税を全て税込で処理した方が、手間がかかりません。
小規模な個人事業主の帳簿作成にかかる手間を、税務署が考慮してくれているのです。
感謝ですね。
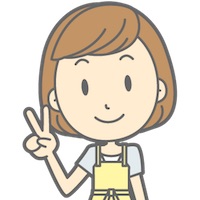
税込経理方式では、全て総額で会計処理します。
消費税の課税事業者は、税込・税抜、どちらか選べます。

課税事業者になると、税込・税別の会計方式を選択できます。
税抜経理方式と税込経理方式、消費税の課税事業者は、どちらか好きな会計方式を選ぶことができます。
ただし、どちらか選んだら、全ての取引を、その会計方式で処理するのが原則です。
消費税を税別で計算する税抜経理方式では、支払った消費税には「仮払消費税」の勘定科目、受け取った消費税には「仮受消費税」の勘定科目を使います。
そして、仮受消費税と仮払消費税の差額が、納税する消費税になります。
また、税込経理方式では、消費税の納税額は、「租税公課」の勘定科目を使います。
税込・税抜、どっちがいいの?、課税事業者の悩み。

結論は、「税込経理方式」プラス「簡易課税制度」です。
税込経理方式と、消費税の簡易課税制度を、併用すること。
これが、個人事業主で、小規模な消費税課税事業者にとっての、ほぼベストな会計処理です。
帳簿作成の手間を考えると、税込経理方式の方が、帳簿は簡単です。
消費税を税別で計算する税抜経理方式では、全ての取引で、それぞれ消費税の金額を計算します。
税込経理方式では、最終的な消費税の納税額の計算は総額で行いまが、個別の取引で、消費税の対象か対象外かを区別する必要はあります。
結局、どちらの経理方式でも、消費税を無視することはできないので、会計アプリを使えば手間はほとんど同じになるんです。

実際には会計アプリを使えば、どちらの経理方式でも、帳簿の手間はほとんど同じです。
固定資産が多い場合は、税抜会計が有利になります。

固定資産税の金額の基準は、税込・税抜の経理方式で決まります。
税込経理方式だと、消費税が固定資産の取得価額に含まれ、消費税分は取得した年に一括して経費とできず、減価償却費として経費にできるまでの期間が長くなってしまいます。
固定資産の取得価額が、消費税の分だけ高くなるので、その結果、固定資産税も高くなってしまいます。

税込経理方式だと、固定資産税が高くなる。
また、税別で99,000円の物は、税込では10万円を超えます。
この時に、税抜経理方式だと99,000円が基準となり消耗品費でOKですが、税込会計方式では10万円を越えるため、固定資産として会計処理する必要があります。
また、20万円未満、30万円未満の、固定資産の特例の金額も、税込・税抜の経理方式によって決まります。
このように、ちょっとでも、固定資産の取得価額を少なくしたい場合には、税抜経理方式が有利になります。

固定資産の10万円の基準も、税別と税込では違いがでます。
消費税の簡易課税制度の活用

簡易課税制度は、ほとんどの個人事業主で、お得になります。
消費税の納税では、簡易課税制度を選ぶと、ほとんどの個人事業主は、消費税の納税額が少なくてすむので、お得になります。
簡易課税制度では、消費税の受け取りは計算しますが、消費税の支払いの計算が不要になります。
そのため、わざわざ税別会計で、支払った消費税を計算する必要がないのです。
固定資産を考えると税抜経理方式が有利ですが、それを圧倒的に上回る有利な制度が、簡易課税制度です。
小規模な個人事業主は、消費税の納税額が少なくなる簡易課税制度がお得なので、固定資産をあれこれ考えるより、税込会計で十分なんです。

個人事業主に有利な会計処理、結論は「簡易課税制度」プラス「税込経理方式」です。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
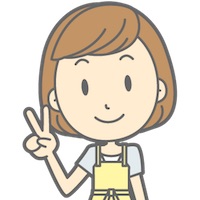
これで私は青色申告しています。
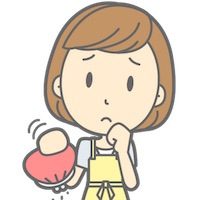
たくさん税金払うの好きですか?









