
青色申告する妻での、夫の所得税の配偶者控除になれます。

会社員の夫と、自営業の妻。
妻の収入が少なくても青色申告すると、夫の扶養から外れてしまう。
これが、よくある誤解です。
収入が少なければ、妻が青色申告しても、全然夫の扶養に入れます。
いろんな具体例で、扶養に入れるか、どうかを紹介します。
収入が少ないっていう基準金額については、一番最後に説明しています。
具体例で解説、扶養に入れる?入れない?

ここでの夫の扶養入るとは、「所得税の配偶者控除」の対象かどうかです。
夫が会社員の場合
会社員の夫、妻は専業主婦

もちろん、この妻は、夫の扶養に入れます。
(夫)=会社員
(妻)=専業主婦(収入無)
この妻は、配偶者控除の対象です。
会社員の夫、妻は自営業

この妻も、夫の扶養に入れます。ここは誤解は少ないところ。
(夫)=会社員
(妻)=自営業(収入少)
妻が自営業でも、収入が少なければ、配偶者控除の対象です。
会社員の夫、妻は自営業

この妻でも、夫の扶養に入れます。
(夫)=会社員
(妻)=青色申告で自営業(収入少)
ここはよく誤解するところ。
青色申告すると、もう夫の扶養に入れない、という誤解があります。
しかし、青色申告でも収入が少なければ、扶養に入れるんです。
むしろ、青色申告の方が扶養に入りやすいんです。
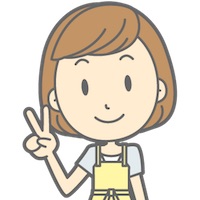
これで私は青色申告しています。
夫が自営業の場合
自営業の夫、妻は専業主婦

夫が個人事業主、妻は扶養に入れます。
(夫)=青色申告で自営業
(妻)=専業主婦(収入無)
この妻は、夫の扶養に入れます。
夫が自営業でも、会社員でも、配偶者控除の条件は同じです。
ここは誤解は少ないところ。
自営業の夫、妻も自営業、夫婦で別の仕事

青色申告していても、妻は扶養に入れます。
(夫)=青色申告で自営業
(妻)=青色申告で自営業(収入少)
ここもよく誤解するところ。
お互いに青色申告でも、どちらかの収入が少なければ扶養に入れます。
自営業の夫(青色申告)、妻も一緒に仕事
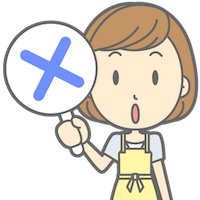
専従者である妻は、夫の扶養に入れません。
(夫)=青色申告で自営業
(妻)=青色事業専従者(収入少)
専従者になると、収入が少なくても、扶養には入れません。
ただし、青色事業専従者の届出だけをしていても、1年間で全く給与を支払ってなく、年収が0円の場合は、扶養に入れます。
自営業の夫(白色申告)、妻も一緒に仕事
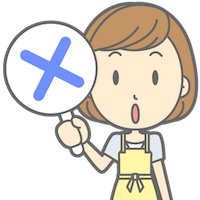
白色でも専従者なら、夫の扶養に入れません。
(夫)=白申告で自営業
(妻)=専従者(収入少)
この妻は夫の扶養に入れません。
そもそも、白色の専従者の給与は、必要経費にできないので、妻の収入が少ないって言葉も、ちょっと変なんですよね。
妻が、白色申告をする夫の専従者になると、専従者控除86万円の定額が、事業所得から控除できます。
扶養に入れる金額、妻の収入がいくらまで?

「夫の扶養に入る」、税金では、所得税の配偶者控除のことです。
税金の扶養、配偶者控除
アルバイトやパートで働く妻の給与が年間103万円までなら、夫の扶養に入れます。
ここでの「扶養に入る」とは、所得税の配偶者控除のことを指しています。
また、妻が独自に自営業をしている場合は、所得が年間38万円まで、配偶者控除の対象になります。
妻が、青色申告の自営業で、特別控除65万円を活用すると、事業で年間103万円の利益まで、夫の扶養に入れます。
- 民法での配偶者(内縁の妻はダメです。)
- 生計が同じである。
- 所得が38万円以下(給与所得では103万円以下)
- 専従者として給与をもらってないこと。
以上の4つが、所得税の配偶者控除の条件です。
ちょっとだけ基準額を超えた時は、配偶者特別控除

配偶者控除の所得金額を超えても、段階的に控除が少なくなる「配偶者特別控除」があります。
- 控除を受ける人は所得1,000万円以下
- 民法での配偶者(内縁の妻はダメです。)
- 生計が同じである。
- 所得が38万円超76万円未満
- 専従者として給与をもらってないこと。
以上が配偶者特別控除の条件です。
夫婦がお互いに配偶者特別控除を受け合うとか、他の人の扶養控除と重複するとかは、条件を満たしていてもNGです。
夫が会社員の場合は、社会保険の扶養がある。

年金と健康保険、社会保険の扶養は収入130万円が基準です。
夫が会社員の場合は、税金が安くなる扶養の他に、年金と健康保険の社会保険の扶養もあります。
これは一律で収入130万円以下が条件です。
所得ではなく、収入が基準です。
税金の扶養より、社会保険の方が影響する金額が大きくなります。
これは自営業にはない、会社員の特権ですね。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
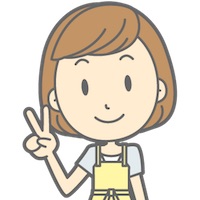
これで私は青色申告しています。
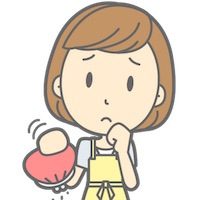
たくさん税金払うの好きですか?









